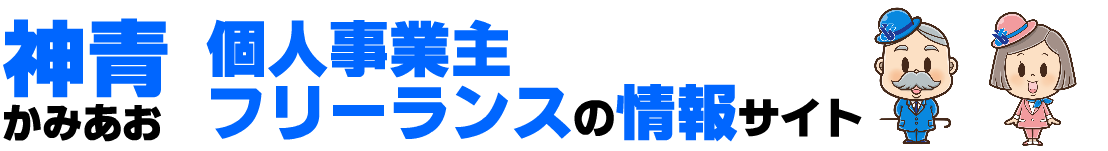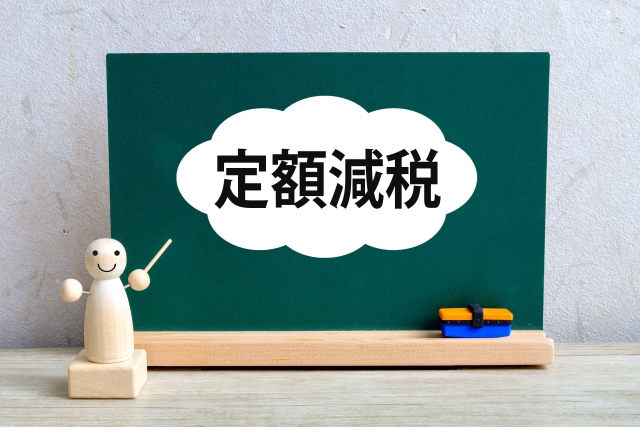前回は対象者、金額、調整給付金についてご説明しました。今回は、実施方法についてご説明します。
定額減税の実施方法
所得の種類によって異なります。
※市町村が条例で独自に納期を定めているときは、実施方法が異なります。
事業所得・不動産所得など
①所得税
予定納税をする人を除いて、令和6年分の所得税確定申告で納付する税額から控除されます。
※令和6年分所得税の予定納税をする人は、予定納税の第1期(納期限:同年7月31日)で本人分の定額減税が控除されます。同一生計配偶者または扶養親族分の定額減税を受けるときは、同年7月31日までに予定納税額の減額申請の手続きをすると、控除されます。なお、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降で順次控除されます。
②個人住民税(普通徴収)
定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)で控除されます。第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降で順次控除されます。
※令和6年度分の個人住民税の税額決定通知書は、定額減税がおこなわれたものが届きます。
公的年金等
①所得税
令和6年6月に支払われる公的年金等の源泉徴収税額から控除されます。控除しきれない場合は、同年中に支払われる公的年金等の源泉徴収税額から順次控除され、最終的には同年分の所得税確定申告で調整されます。
※「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出した場合は、源泉徴収時に配偶者や扶養親族分の定額減税額が控除されます。
※公的年金等の受給者で事業所得など他の所得がある人は、最終的に確定申告で調整します。
②個人住民税(特別徴収)
令和6年10月に支払われる公的年金等の特別徴収(定額減税前の年税額をもとに算出された金額を徴収)で控除されます。控除しきれない場合は、令和6年度内に支払われる公的年金等の特別徴収で順次控除されます。
※公的年金等から個人住民税が初めて特別徴収される場合は、令和6年の6月分と8月分は普通徴収となり、同年10月分から特別徴収となります。
給与所得
①所得税
令和6年6月1日以後、最初に支払われる給与等の源泉徴収税額から控除されます。控除しきれない場合は、同年中に支払われる給与等の源泉徴収税額から順次控除されます。
②個人住民税(特別徴収)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の年税額を同年7月から令和7年5月までの11ヶ月でならした税額が徴収されます。
※給与所得者に対する定額減税は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先においておこなわれます。
詳細はこちらをご覧ください。
経済を好循環へ 定額減税を実施します|首相官邸ホームページ (kantei.go.jp)
定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税について (soumu.go.jp)